「犬と一緒にアロマを使ってみたいけど、本当に大丈夫かな?」そんな疑問や不安は、実は多くの飼い主さんが抱えているものです。
人にとっては心地よい香りも、嗅覚が敏感な犬にとっては“強すぎたり負担”になってしまうことがあるからこそ「ちょっと気になる」「不安かも」という感覚はとても自然で、大切な気づき。
この記事では、
犬の嗅覚の話や犬が一緒でも「使える精油」と「避けたほうがいい精油」、犬にも優しいアロマスプレー(アルコール不使用(無水エタノール不使用/ノンアルコール)の作り方から使い方、注意点まで、幅広く書いています。
読み終えたとき、「これなら犬が一緒でも安心してアロマを試せる」と感じてもらえたら嬉しいです。
犬の嗅覚と代謝|アロマを安全に使うために知っておきたいこと

まずは、犬の嗅覚は人よりはるかに鋭く、香り成分の代謝(体内処理)も人と違うということを知っておくことが大切です。
「ほんのり香る」くらいでも、犬にとっては実は“強烈”に感じられているからこそ、人と犬の嗅覚や体の仕組みの違いをちょっと知っておくだけで、安心度がグッと高まります。
ここではそのポイントをわかりやすくお伝えしますね。
なぜ人が感じる「ほのかな香り」が犬には強いのか?(嗅覚数値の目安)

犬の嗅覚って「すごい!」とよく聞きますが、実際どのくらい違うのかピンときにくいですけど、数値にしてみると、人との感覚差がはっきり見えてきて、「やっぱり注意してあげなきゃ」と納得できるはずです。
というわけで、まずは犬の嗅覚に関することをざっくりと簡単な数値でお伝えしておきます。
- 嗅覚受容体数(概数):
【人間】嗅細胞は約500万〜1000万個存在し、約387〜400種類の嗅覚受容体を持つとされています。
【犬】嗅細胞は約2億2千万個〜3億個(犬種差あり)とされ、嗅覚受容体の種類は約811〜1094種類と報告されており、人の約2倍以上です。 - 嗅上皮の面積:
【人間】約3〜10cm²
【犬】 約18〜150cm²(最大で170cm²とされる場合もある) - スニッフィング(短い呼吸で連続的に嗅ぐ):毎秒〜5回=短時間でも取り込みが多くなりやすい
上記のような感じで、
犬は人の数十倍から数百倍に及ぶ嗅細胞数と約2倍以上の嗅覚受容体の種類、そして人の数倍から数十倍に広がる嗅上皮を持つため、その嗅覚能力は人の数千倍から1億倍にもなると言われるほど、圧倒的に優れているのです。
数値か大きすぎてピンとこないかもしれませんが、匂いを感知する能力が格段に優れているからこそ、
人からすれば“ほのかな香り”が、犬には強すぎることがあるというのを数値にすれば何となくは理解できますよね。
これを前提としたうえで、これから一緒に犬とアロマテラピーの基本について考えていけたら嬉しいです。

犬と一緒にアロマを使う安全の基本ルール
先ほどの数値を見れば分かると思いますが、犬とアロマを楽しむには、薄く(低濃度)・短く(短時間)・換気(空気を流す)、この3つが安全性を守るうえで重要です。
他には犬が自分の意思で離れられるような開放性(ドアを少し開けておく、別室を確保など)があると、犬の負担を減らしやすくなるので尚良いです。
犬と一緒にアロマを使う前に|安全チェックリスト
「今日は大丈夫かな?」と迷ったときに、そのまま使うのは不安ですよね。
そんな時に役立つのが、このチェックリスト。始める前に確認するだけで、犬を守る安心感が違ってきます。
下記の中でひとつでも気がかりな事があれば、今日はアロマを使わない!という判断に切り替えやすくなりますので、参考にしてみてください。
- 体調:咳・鼻水・吐き気・下痢など、いつもとの差は?(少しでも迷ったら使わない)
- 環境:換気できる?退避ルート(開いたドア・別室)は確保できた?
- 同居動物:猫・小鳥・フェレットが同室にいない?(同室なら使わない)
- 見守り:開始後30分は様子を見ていられる?
ひとつでも怪しいなら、今日アロマを使うのは見送りにした方が良いかもしれません。
犬と一緒に使う精油の選び方(まず“使わない”を決める)

安全は足し算より引き算から。 先に“使わない精油を決める”ことで、残った精油候補から自信もってアロマを選びやすくなります。
犬に使わないほうが良い精油一覧
まずは犬と一緒に使わないほうがよい精油を、理由つきで短くお伝えしていきます。
ティーツリー/ペニーロイヤル/ウィンターグリーン/スイートバーチ/シナモン/クローブ/ペパーミント/パイン/ユーカリ/イランイラン など
上記の種類を避ける精油として挙げた理由は、
刺激が強い、事故報告がある、サリチル酸系・フェノール系など成分特性のリスクが高いため。
精油別に、避けたほうがいい理由を簡単解説
- ティーツリー(未希釈や誤飲で不調報告)
- ペニーロイヤル(肝負担懸念)
- ウィンターグリーン・スイートバーチ(サリチル酸メチルが非常に多い)
- シナモン・クローブ(アルデヒド/フェノールで刺激・感作)
- ペパーミント(メントールで気道刺激)
- パイン(揮発成分が刺激)
- ユーカリ(1,8-シネオール高含有)
- イランイラン(香りの圧が強い、感作報告あり)
犬と一緒の空間で扱いやすい精油(低濃度・短時間・換気が前提)
“OK=いつでも安心”ではありませんが、比較的安全なアロマ精油をご紹介します。
※個体差・濃度・時間の影響が大きいため、直接塗布は行わず、短時間で反応を見ながら扱います。
- ラベンダー(真正):主成分がリナロール/酢酸リナリルで、刺激性フェノールやケトンが少なめ。香りはしっかりしていても過剰刺激になりにくく、安心して使える万能精油。
- ローマンカモミール:エステル類中心で穏やかな精油。においの角が立ちにくく、成分も優しめで使用しやすい(キク科に敏感な個体はパッチテスト推奨)。
- フランキンセンス:モノテルペン中心で立ち上がりが急すぎない樹脂調であり、空間使用で香りの輪郭が丸くなりやすく、刺激感が出にくい傾向。
- ゼラニウム:シトロネロール/ゲラニオール由来のフローラル調で、香りの圧はやや強めでも、濃度を抑えると扱いやすくなります。
- マンダリン/オレンジ・スイート:光毒性の懸念がない柑橘系の精油。主成分であるリモネンは酸化で刺激が出やすいため、新鮮なものを少量・短時間でするなら扱いやすい。
- パルマローザ:ゲラニオール主体でやさしく広がる香りが特徴で、刺激もさほど強くなく扱いやすい。
※猫が同居している場合は、同室での拡散は避けましょう。
犬用アロマスプレーの作り方

犬と一緒でも使えるアロマスプレー、「使ってみたいけど、市販のはちょっと不安…」という方も多いかと思います。
でも、実はご家庭でも犬にやさしいアロマスプレーは簡単に作れるんです。
ここからは安全性に配慮した2種類の作り方をご紹介します。
- 空間用:精油を超低濃度で可溶化し、同じ空間でふんわり香らせるスプレー。
- 直接ケア用:犬の被毛・皮膚にやさしく使えるスプレー(精油は使わず、ハイドロゾル=芳香蒸留水/フローラルウォーターをベース)。
① 空間用(精油入り/超低濃度・ポリソルベート使用)※グリセリン、アルコール不使用
まずは犬が一緒でも安心して使える空間用のスプレーからお伝えしていきます。
前提:精油は水やグリセリンには溶けません。
「水+精油だけ」だと分離して局所的に高濃度が皮膚・粘膜に触れるリスクが残る可能性が高いため、
犬への刺激を抑えるようソルビライザー(例:ポリソルベート20)という乳化剤の一種を使って均一に混ざるようにします。
アルコール vs ポリソルベート(要点)
- アルコール:溶解・保存性に寄与するが、揮発時の立ち上がりが強く、犬の鼻・粘膜に刺激になりやすい。
- ポリソルベート:精油を水に均一分散(局所高濃度の低減)。合成界面活性剤のため完全ナチュラル志向とは異なるが、適正量ならアルコールより安全寄りにしやすい。
というわけで、グリセリンでもなく、アルコールも犬とってはキツイので使用しません。
アルコール不使用レシピ:超低濃度・アロマスプレー(100mL)
- 精製水 … 100mL
- 精油 … 1〜2滴(最終濃度の目安 0.05〜0.1%)
- ポリソルベート20 … 精油の4〜5倍の滴数(例:精油2滴 → 8〜10滴)
手順:
1) 小さなカップで精油+ポリソルベートを先にしっかり混ぜる
2) 清潔なボトルに精製水を7〜8割入れ、1)を加える
3) 残りの水を入れて全量100mLにし、ふたを閉めてしっかり混ぜる
4) ボトルに作成日ラベルを貼る(少量作製・早期使い切り(2週間以内)
- 使い方(やさしい運用):犬のいない方向へ上向きに1プッシュして30分観察します。
床やベッドへは直接向けず、犬がいつでも離れられるように換気と退避ルート(開いたドア/別室)を確保し、問題がなければ次回は同条件で2プッシュくらいまで使用。 - 保管・衛生:器具・ボトルは清潔・完全乾燥し、直射日光・高温を避け、2週間以内を目安に使い切る。
分離は起きにくいものの、使用前に軽く振ると安心です。
※滴数は一般的に20滴=1mL(1%)目安。
材料メモ:
ポリソルベート20…化粧品原料ショップ、アロマ資材店、大手EC。「ポリソルベート20」で検索。
精製水・スプレーボトル…ドラッグストア、ホームセンター、100均など。
② 直接ケア用(犬の被毛・皮膚に使えるハイドロゾルスプレー)
前提:犬の皮膚や嗅覚は敏感なので、直接使うスプレーに精油は基本的に入れません。
代わりにハイドロゾル(=芳香蒸留水/フローラルウォーター)を使うと、日常ケアとして犬にも使えてやさしく取り入れやすくなります。
レシピ(100mL)
- ハイドロゾル(フローラルウォーター) … 100mL(例:ラベンダー/ローズ/ネロリ/ローマンカモミール など)
使い方:
・背中の被毛に軽く1プッシュ→ブラッシングでスルスルとなじませる
・顔・鼻・口・目・粘膜まわりは避ける
・初回はごく少量→30分観察。小型犬・子犬・シニア・皮膚が繊細な子は、さらに少量・低頻度から。
保管:直射日光・高温を避け、できれば冷蔵保管し、2週間以内を目安に使い切る。もちろん、ボトルは清潔・完全乾燥で。
おすすめのハイドロゾル:ラベンダー(リラックス)/ローマンカモミール(肌をいたわりたい時、キク科に敏感な子は様子見から)/ネロリ(落ち着き+保湿)/ローズ(香りはやや強め。繊細な子は少量から)。
入手先:アロマ専門店、化粧品原料ショップ、大手ECで「ラベンダーウォーター」等で検索。開封後は品質変化しやすいので小容量からがおすすめ。
犬用アロマのやさしい使い方(共通ルール)

せっかく作ったスプレーも、使い方を間違えると犬に負担をかけてしまうことも…。
ここでは「どのスプレーでも共通する安心ルール」をシンプルにまとめました。
- 向き:犬のいない方向へ上向きにスプレー。
- 時間:短時間(初回5〜10分)→30分観察。
- 環境:換気と退避ルートを確保し、嫌がる素振りがあれば中止→換気。
フローラルウォーターの犬用スプレーなら、自分の手に吹きかけてから犬の背中を優しくなでるようにするのもいいですね。(特に顔・鼻先など)。
犬にアロマを使ってトラブルが起きた時の対処法

「もし嫌がったらどうしよう…」そんな不安は誰にでもありますよね。でも大丈夫です、事前に対処法を知っておけば、慌てず落ち着いて対応できます。
- 香りが強い/犬が離れたがる:使用量・時間を半分に。精油使用ならより穏やかな種類へ切替、またはハイドロゾルに。
- べたつく:可溶化(水と精油の均一化)が不十分かもしれないので、ポリソルベート比率を見直すか、ハイドロゾルへ切替。
- 猫が同居:同室拡散は避け、別室+換気+退避を徹底。
- 体調サイン(咳・くしゃみ・嘔吐・落ち着きのなさ等):使用中止+換気。改善しなければ受診を。
犬とアロマを安心して楽しむためのまとめ

たくさんの情報を聞くと「難しそう」と感じるかもしれませんが、基本を押さえれば安心して取り入れられます。
最後に、今日お伝えした大切なポイントをギュッとまとめました。
- 空間用スプレー:精油はポリソルベートで可溶化し、精油濃度は0.1%未満・短時間・換気・退避ルートが基本。
- 直接ケア用スプレー:精油は入れず、ハイドロゾル(芳香蒸留水/フローラルウォーター)を第一候補に。
- 香りは脇役。主役は犬。、ワンちゃんの様子を見ながら寄り添うこと自体が、いちばんやさしいアロマテラピーです。
よくある質問(FAQ)
「結局どれを選べばいい?」「ティーツリーは本当にダメ?」など、気になる疑問は尽きないもの。そこで多く寄せられる質問をまとめ、シンプルにお答えしていきます。
Q. 結局どれを選べばいい?(ハイドロゾル/ポリソルベート/アルコール)
A. 安全度の優先順位は、ハイドロゾル > ポリソルベート可溶化 >(避けたい)高濃度アルコールです。
ハイドロゾルは超希薄で扱いやすく、精油を使う場合はポリソルベートで0.1%未満にしてください。
- 空間用は、ポリソルベートと精油使ったアロマスプレー
- 犬用は、精油を使わないハイドロゾル(フローラルウォーター)のみのアロマスプレー
Q. 人用ルームスプレーを薄めて犬に使える?
A. 推奨しません。成分・濃度・溶媒が不明ですし、犬には香りや成分が強すぎになりやすいからです。
Q. ティーツリーは“ほんの少し”なら?
A. 避けます。少量でも不調報告があり、家庭ケアではメリットよりリスクが先行します。
Q. 猫も同居しています。どうすれば?
A. 同室拡散は避けるようにし、別室+換気+退避を徹底。迷う場合は使わない選択が安心です。
参考文献(URL付き)
- Jenkins EK, et al. When the Nose Doesn’t Know: Canine Olfactory Function. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5884888/
- Berg P. Olfaction in the canine cognitive and emotional processes(2024 レビュー)PDF: こちら / 概要: こちら
- Staymates ME. Biomimetic Sniffing Improves the Detection Performance…(Scientific Reports, 2016)https://www.nature.com/articles/srep36876
- Spencer TL, et al. Sniffing speeds up chemical detection…(Proc. Royal Society B, 2021)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7902652/
- Khan SA, et al. Concentrated tea tree oil toxicosis in dogs and cats.(JAVMA, 2014)PubMed / JAVMA
- Merck Veterinary Manual:Toxicoses From Essential Oils in Animals. https://www.merckvetmanual.com/toxicology/toxicoses-from-household-hazards/toxicoses-from-essential-oils-in-animals
- VCA(犬):Essential Oil and Liquid Potpourri Poisoning in Dogs. https://vcahospitals.com/know-your-pet/essential-oil-and-liquid-potpourri-poisoning-in-dogs
- VCA(猫):Essential Oil and Liquid Potpourri Poisoning in Cats. https://vcahospitals.com/know-your-pet/essential-oil-and-liquid-potpourri-poisoning-in-cats
- Pet Poison Helpline:Updates on Essential Oils. https://www.petpoisonhelpline.com/blog/updates-on-essential-oils/
- Tisserand Institute:Bath Safety(分散の要点、Polysorbate 20/80)https://tisserandinstitute.org/safety/bath-safety/ / Dispersing essential oils https://tisserandinstitute.org/learn-more/dispersing-essential-oils/
- Formula Botanica:Solubiliser vs. Emulsifier(可溶化剤と乳化剤の違い)https://formulabotanica.com/solubiliser-vs-emulsifier/ / How to use a natural solubiliser https://formulabotanica.com/how-to-use-a-natural-solubiliser/








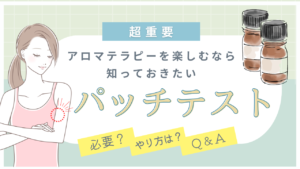
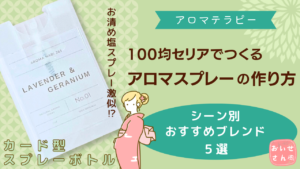
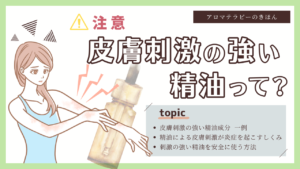
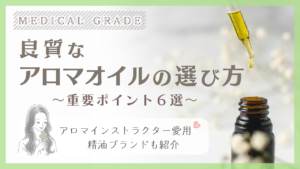

コメント